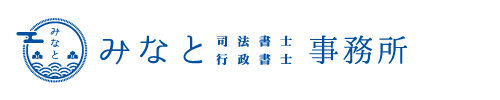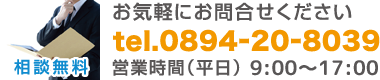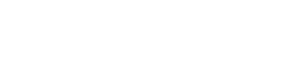相続した空き家の「3,000万円特別控除(空き家特例)」ってなに?
相続で手に入った「被相続人が住んでいた家(とその敷地)」を、相続開始から3年以内の年末までに売るなど、一定の条件を満たすと、譲渡益から最大3,000万円を差し引ける制度です。
ざっくりいうと、「古い空き家を相続したら、早めに売れば税金がとても安くなる特例」です。
前提の状態(手続き前の不動産登記の名義)
土地:名義人=母
建物:名義人=父
※父が先に死亡し、その後母が死亡という事案
どこが落とし穴?(父→母と順に亡くなったケース)
父が亡くなり、その後に母が亡くなった——この順番のあとで売却する場面では、司法書士としてはつい
・「建物(父名義)→ 子へダイレクト」
・「土地(母名義)→ 子へダイレクト」
とそれぞれ直接、相続人名義にしてしまいがちです。
ですが空き家特例は、家と土地を“同じ被相続人”から相続で取得していることが実質的な前提です。
したがってこのケースでは、
・建物は「父 → 母」の相続登記を経る(父の持っていた建物を、まず母に承継)
・そして土地・建物の両方を「母の相続財産」として相続登記したうえで売却する。
という名義のそろえ方をしておかないと、特例が使えないリスクが高まります。
2024年9月2日の東京地裁判決でも、名義の持っていき方を誤った結果、特例不適用と判断されています。
司法書士・税理士として知っておくべき点
専門家として知っておくべきポイントは、建物と土地の「取得元(被相続人)」を一致させる遺産分割をすべき——すなわち、建物は「父→母」を経て、最終的に「母の相続財産」として土地と建物を一体とする相続登記(数次相続)してから売却へ、という順序を守らなければ3,000万円特別控除(空き家特例)を使えないという点です。
ちなみに
父から子へ直接行ってしまった登記は、いったん抹消したうえで、正しい順序(父→母→子)で再度登記し直すことが可能です。
したがって、売却前にこの「抹消・再登記」を済ませていれば、要件や期限を満たすことを前提に、空き家特例を利用できる可能性はあります。
もっとも、令和6年9月2日の東京地裁判決では「仮に遺産分割協議をやり直したとしても、それは新たな処分行為とみなされるため特例は適用されない」と消極で判断されていますので、実際にやり直しを検討する際には、担当者に事前確認を行い、適用の可否を確かめたうえで進めるのが無難でしょう。