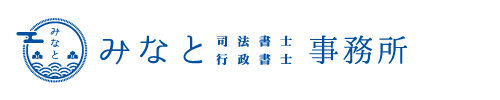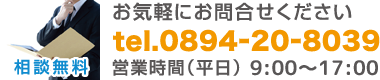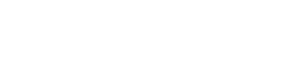いわゆる「負」動産の放棄について
最近は資産ではなく、負債にしかならない不動産のことを「負」動産と言ったりします。
相続登記が義務化されたことを受け、これまで先代名義のまま相続登記を行わず、固定資産税だけを支払い続けていた方々も、ようやく重い腰を上げ始めました。その結果、長期間放置されていたために相続人が増え、遠くの親戚に連絡を取って実印や印鑑証明書の協力をお願いするケースが急増しています。しかし、突然「登記に協力してほしい」と連絡を受けた親戚にとって、何代も前に亡くなった方の不動産がまだ残っており、自分が相続人になっていることに驚くのも無理はありません。特に、使い道のない田舎の土地に関しては、関わりたくないと感じる人が多いようです。(なお、相続人の所在が不明な場合には、司法書士等に依頼して調査を行い、住所を突き止めて手続きを進めることも可能です。)
誤解されがちですが、先代名義のまま放置されている不動産については、たとえ誰かが固定資産税を20年以上代表して支払っていたとしても、法律上は相続人全員がその不動産を共有しているものと扱われます。したがって、本来であれば固定資産税の負担も相続人全員が分担する必要がありますし、その不動産について他人に損害を与えた場合、相続人全員が損害賠償の責任を負う可能性があります。
そのため、突然相続登記の協力を求められた方にとっては、自分が協力したとしても、相続人が多すぎたり、不動産を誰も欲しがらなかったりする場合には、相続登記がスムーズに進まず、気づかないうちに3ヶ月が過ぎてしまう可能性があります。そのため、不動産の存在を知った時点(代表相続人から通知を受けたとき)から3ヶ月以内に、速やかに相続放棄を検討することをお勧めします。こういったケースでは、何十年経過していても、不動産の存在を通知された時点が「知ったとき」になるため、その時から3か月以内であれば相続放棄が認められる可能性が高いです。少なくとも私が担当した案件については、相続放棄が認められなかったことはありません。
ちなみに、時間が経過すればするほど相続関係が複雑になり、特に当初の相続人が死亡していて、さらに相続が発生しているような状態(数次相続といいます)である場合、相続放棄の手続きそのものの難易度も高くなります。一般の方にとっては、どの司法書士等に相談しても相続放棄の可否は変わらないと思われるかもしれません。しかし、実際には、他の事務所で「あなたのケースでは相続放棄ができない」と言われた場合でも、詳しく話を伺うと、相続放棄が認められる可能性が十分にあるのに、なぜ断られたのかと感じることが少なくありません。実際、他の事務所で「この案件は相続放棄できない」と判断されたケースを私が引き受け、最終的に相続放棄が認められた例も多々あります。
特に、当事務所では都会にお住まいの方からの相談が目立ちます。「都会に住んでいるが、先代が田舎に残した不動産があることがわかった。近所の専門家に相談したところ、相続放棄はできないと言われたので、地元の司法書士にも相談してみようと思って電話しました」というケースも多いです。こうした案件は、経験豊富な事務所でなければ対応が難しいことがあります。そのため、一つの事務所で断られた場合でも、セカンドオピニオンとして他の事務所に相談してみることをお勧めします。