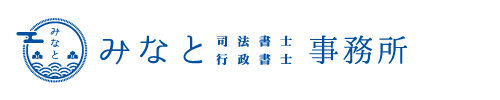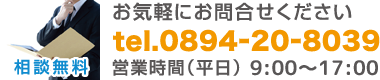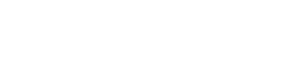3ヶ月経過後の相続放棄は決して珍しいものではありません。
法律の規定では「相続があったことを知った時から3ヶ月以内に」と定められていますが、家庭裁判所での判断は法律の規定どおりに機械的に行われるわけではありません。
実際、私が今まで手続きしてきた案件も約半数は3ヶ月経過後の相続放棄です。
3ヶ月経過後に相続放棄が認められるためには、「3ヵ月以内に相続放棄しなかったことについて、相当の理由がある」ことが必要です。
3ヶ月経過後の相続放棄が認められる条件
前述の「相当の理由」を裁判所に説明する前提として、「亡くなられた方の資産や負債の存在を知った時から3ヶ月経過していない」という条件を満たしている必要があります。
他にもいくつかポイントはありますが、この条件が最も重要です。
実際、今まで私が代行した案件も、この条件を満たしていれば、全て相続放棄が認められています。
では、なぜ上記の条件が重要なのでしょうか?
それは、資産や負債の存在を知らなかったのであれば、相続放棄を検討するきっかけすらなかったはずだからです。
そして、検討するきっかけすらなかったのであれば、相続放棄をできていなくともやむを得ないため、「相当の理由」があったと裁判所に対して説明しやすくなります。
したがって、「亡くなられた方の資産や負債の存在を知った時から3ヶ月経過していない」という条件を満たしていれば、相続放棄を認めてもらえる可能性はとても高いのです。
借金についての通知が来たら
お客様の中には、債権者等から借金に関する通知が届いても、「自分には関係がない」と思い込んで放置される方がいらっしゃいます。
しかし、通知によって負債の存在を知りながら相続放棄の手続きを行わなかった場合、裁判所からは「相続放棄を検討する機会があったにもかかわらず、適切な対応を怠った」と判断され、相続放棄が認められないおそれがあります。
そのため、債権者等から通知が届き、それによって負債の存在を知った場合には、必ずその日から3か月以内に相続放棄の申述を行ってください。
また、通知が届いていない場合でも、債権者や親族などからの連絡によって負債の存在を知った場合には、その連絡を受けた日から3か月以内に相続放棄の申述を行う必要があります。
なお、債権者から届いた通知書は、負債の存在を知った日を証明する重要な資料となります。裁判所に提出する際には、通知書だけでなく、消印のある封筒もあわせて提出する必要がありますので、これらは決して破棄せず、大切に保管しておいてください。
相続放棄が却下されたら、2度目の相続放棄申述はできません
相続放棄の申述が、家庭裁判所に却下されてしまった場合、再度の申立をすることはできません。
そのため、まずは自分で家庭裁判所に行って手続きしてみて、うまく行かなかったら専門家に相談しようというわけにはいきません。
相続放棄の申述が受理されるチャンスは一度きりですから、却下されてしまってから後悔しても手遅れです。
特に3ヶ月経過後の相続放棄申述においては、最初から専門家に相談、依頼することを強くオススメします。
3ヶ月経過していても諦めず、慌てず、まずは相談ください。
お客様にとって、相続手続きは一生に何度も経験することではありませんので、たくさんの不安な点や不明な点があるのは当然のことです。
どんな些細なことでもかまいません。ご相談お待ちしております。